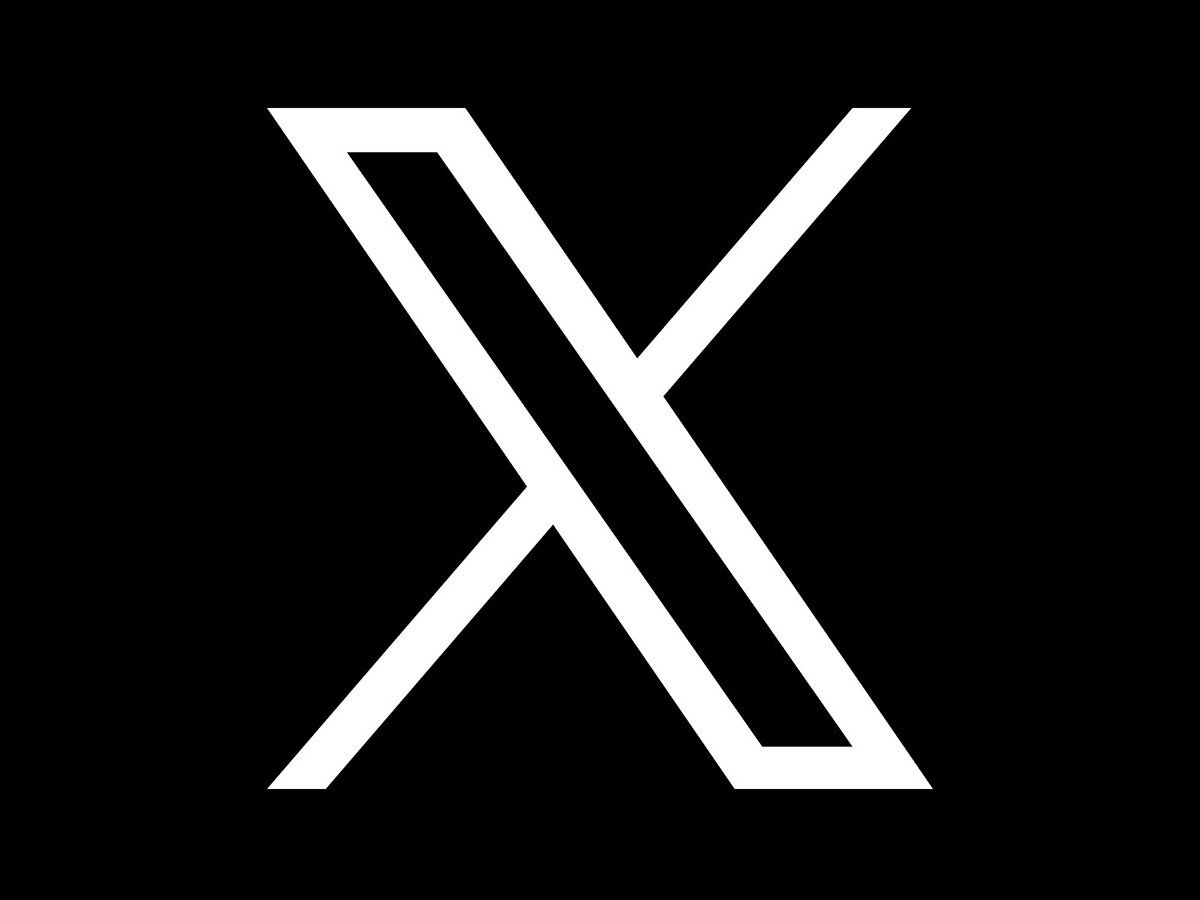 ポスト
ポスト
※この論文はフィクションです
――迷惑プレイヤーという存在の内的必然性に関する一考察――
著者:キョロ(ミスカトニック大学 遊戯共同体論研究室) / 発表年:2025年
本研究は、テーブルトークRPG(以下、TRPG)において頻発する「迷惑プレイヤー」とされる行動様式の内的動機と外的要因を多面的に分析し、彼らの行動が単なる逸脱か、あるいは構造的・環境的要因に根ざした必然かを検討するものである。
315の実セッション、810名へのアンケートおよび半構造化インタビューを通じて、迷惑行動の発生には個人的な性格傾向に加えて、社会的排除経験、情動的抑圧、対人回避傾向、そして承認欲求の歪な表出が強く関連していることが明らかとなった。TRPG空間は彼らにとって最後の社会参加空間であり、逸脱的行動はしばしば“孤独な叫び”として観測される。
TRPGはプレイヤー間の即興的な協働によって物語を形成するメディアであり、その性質上、参加者の振る舞いは即座にゲーム全体に影響を及ぼす。しばしば観測される「迷惑プレイヤー」は、過度な自己主張、ルールへの固執、他者の発言の妨害、感情的暴発、そして不参加とも言える沈黙など、多様な形でセッションの進行を妨げる。
だが果たして、迷惑とは誰にとっての迷惑なのか。
場の進行を乱す者が即座に“悪”とされる現代のTRPG文化において、「迷惑プレイヤー」というレッテルは、しばしば社会的強者によって、社会的弱者に貼られる道具にもなりうる。これは「ゲーム内の秩序」を盾にした、ある種の排除装置ではないのか。
本論文では、迷惑プレイヤーの行動特性そのものに加え、彼らがなぜそのように振る舞うのか、そして我々はなぜ彼らに苛立つのか――という二重の構造を分析していく。
分析の結果、迷惑行動は主に以下の6類型に分けられた:
<報告される被害>
o セッション時間の進行遅延(平均23分の遅延が発生)
o 他PLの発言機会減少(最大でPL5人中4人が20分以上無言)
o 「観客化」による他PLの離脱報告(5件)
<被害と実害>
o GMとの衝突率が最も高く(37%のセッションで口論発生)
o 「自由な発想を封じられた」とするPLの報告多数(74件)
o 一部セッションではルール論争で時間切れ終了(12件)
<被害と背景>
o GMの進行判断が困難になり、テンポ崩壊
o 他PLのストレス増加(「返答が来ない不安」「話しかけても無反応」)
o セッション後のアンケートで「最も対応が難しいタイプ」と評された
<被害報告>
o シーン中断・議論時間平均19分
o 他PLからの報告:「議論の空気でロールプレイが吹き飛んだ」
o 長期キャンペーンでの途中脱退・解散に発展した例あり(4件)
<実害>
o セッションバランスの破綻(NPCの難易度調整が困難に)
o 他PLの「協力による成功体験」が損なわれる
o 成功を演出しようとしたGMとの衝突例も(23件)
<深刻な影響>
o SNS等での晒し行為(8件)
o グループ崩壊、相互ブロック等への発展(16件)
o GMへの長文抗議DM等、TRPG外でのストレス化
迷惑プレイヤーが目立つようになった、あるいは増えてきたと感じられる背景には、単なる個人の資質だけでなく、現代のTRPG環境そのものが抱える構造的問題が関係している。
かつてTRPGは、ルールブックを読み込み、ある程度の準備と覚悟をもって遊ぶ“コアな趣味”であった。しかし現在は、動画配信やSNSによってその敷居が大きく下がり、「とりあえずやってみたい」「雰囲気が好きだから」といった軽いきっかけで参入する層が増えた。
これは歓迎すべきことでもあるが、同時に「マナーや前提を理解しないままリングに上がる者」が増えたという事実もある。例えるなら、プロレスの技を見てテンションが上がった子どもが、ルールを知らずにリングに飛び込んでしまうようなものである。
キャラ語りやロールプレイはTRPGの醍醐味であるが、SNSや動画文化が進化したことで、「自キャラを見てほしい」「盛り上げたい」という承認欲求が暴走しやすくなっている。
「泣き演技を割り込ませる」「オチを無理やり取る」「感動シーンに乱入する」などの行為は、しばしば“目立ちたい”という一心から行われるが、当人に悪意がない分、制御が困難である。
TRPGシステムは現在、多様なスタイルと哲学を持つタイトルが並び立っている。CoC、シノビガミ、インセイン、エモクロア、PBTA系──それぞれに求められるプレイスタイルは異なる。
しかし、「どういう卓で遊ぶのか」の共有が不十分なまま遊び始めた結果、「え、それアリなの?」「なんか嫌だった……」という違和感が生まれる。
特に動画で“演出的で感情的なプレイ”を見た者が、実際の卓で同様の行動を模倣して齟齬を生むケースが多い。
人気リプレイ動画などで、破天荒なキャラクターや場を引っ掻き回す言動がバズると、それを真似するプレイヤーが出現する。彼らは「盛り上げるため」「ウケるから」という意図を持って行動しているが、その背後には本質的な“誤読”が存在する。
迷惑行動が“演出”として持ち上げられ、正当化される土壌が、無自覚な暴走を助長しているのだ。
調査でも示されている通り、迷惑行動はしばしば、現実における自己肯定感の低さ、社会的孤立、他者との非対話的経験によって裏打ちされている。
自分に自信がなく、現実で評価される場を持たず、TRPGの卓上で「自分が主役になれる」と感じた瞬間、彼らは他者を押しのけてでも発言しようとする。
その行動はしばしば“無意識”であり、“善意”であり、そして“迷惑”である。
迷惑行為が卓中で指摘されないのは、「空気が悪くなる」「GMの負担が増える」「SNSで炎上されるかもしれない」といった理由がある。
現場では“やんわり注意”しかできず、その結果、周囲が我慢を強いられる構造が定着している。これはPL間の対等性を崩し、協力ゲームとしてのTRPGの土台を危うくする要因となる。
こうした要素が絡み合った結果、現代においては迷惑プレイヤーが“生まれやすく”“可視化されやすく”なっている。
“昔はこんなPLいなかった”のではなく、今は出会ってしまいやすい環境が整ってしまったということである。
ゆえに、現代のPLにはこれまで以上に「自分は協力型の遊びに参加している」という意識と、自分の言動が他者にどう影響しているかを想像する力が求められているのである。
Oso18という熊は、かつて北海道の山林に生息していた。体は他の雄グマに比べて小さく、力も弱く、木の実をめぐる縄張り争いでは常に負け、豊かな餌場からは追われていた。つまり彼は、熊社会における“社会的弱者”であった。そして、木の実も鹿も手に入らなかった彼が、最後に選んだのが人里に降りて牛を襲うという手段だった。彼は迷惑な熊と呼ばれ、報復され、殺された。しかし、それは本当に“迷惑”だったのだろうか。
彼は、木の実を食べて生きたかっただけだ。
TRPGにおける迷惑プレイヤーもまた、同様である。彼らもまた、発言力のあるPLやGM、交流能力に優れた参加者との“縄張り争い”に敗れ、卓内の快適なポジションを確保できず、社会的視点で言えば“弱者”である。
居場所がない者、声が通らない者、自信を持てない者。
彼らが唯一行使できる力は、卓における“暴力的な演出”や“ルールの強制”といった疑似的な支配行動だけである。
迷惑行動とは、社会的エネルギーの“最終形”である。それはしばしば攻撃的に見えるが、実態としては社会的孤立という名の飢餓状態が生み出した、低質な自己主張にすぎない。
TRPGにおける迷惑プレイヤーも同様である。現実に居場所を持たず、発言権を奪われ、他者と語る言葉を失った者が、TRPGという小さな社会に“襲いかかる”。だがそれは、彼らにとってここが唯一の“餌場”であり、縄張りであるからに過ぎない。
TRPGという場は、幻想の世界であると同時に、彼らにとって最後の現実である。そこにおける逸脱は、むしろ彼らが「まだ、諦めていない」ことの証かもしれない。
迷惑プレイヤーを排除することは簡単だ。だがそれでは、彼らの存在の背後にある社会的痛みや個人的苦悩を覆い隠すことにしかならない。
迷惑プレイヤーとは、“TRPG空間においてしか生きる資格を持てなかった者”なのかもしれない。彼らの逸脱行動は、「自分を見てほしい」という未成熟な叫びであり、それはやがて社会の別の断層と繋がっていく。
迷惑を責める前に、なぜ彼らがそうせざるを得なかったのか。誰が彼らをそうしたのか。そして、TRPGは果たして彼らにとってどんな“最後の砦”だったのか。
それを、我々は忘れてはならない。
※これは論文風のパロディサイトです。内容は事実を基にしたフィクションであり、調査データや参考文献等はすべて架空です。