NPCの目線に立てば、世界が変わる
4/25 2025
カテゴリー:GM・物語との関わり編

ChatPTによるこの記事の3行要約
- NPCを機能ではなく、感情を持った『誰か』として想像する視点が物語を変える。
- 共感型プレイは、技能よりも、相手の立場を考える想像力でドラマを生む。
- 「どう利用するか」ではなく、「なぜそうしているのか」を考えた瞬間、世界が生き始める。
1. NPCは『語り部』ではなく、『生きている誰か』かもしれない
クトゥルフ神話TRPGをプレイしていると、数多くのNPCと出会う。
協力者、情報提供者、敵、犠牲者、狂気の担い手、悲劇の語り部──
物語を動かすために配置された彼らは、しばしば『機能』としてそこに現れる。
けれど、少しだけ視点を変えてみてほしい。
「このNPCは、今何を考え、なぜこういう行動をしているのか?」
情報をくれないNPCに苛立つ前に、その人の気持ちを想像してみる。
恐怖で言葉にできないのかもしれないし、過去と向き合いたくないのかもしれない。
そこに一歩、寄り添ってみたら──それは『対話』ではなく、『関係』になる。
2. 共感型プレイが生み出す『沈黙のドラマ』
共感型のプレイとは、技能や設定に頼らず、「相手の心を想像する力」で物語を深めていくプレイスタイルだ。
- この人の立場だったら、何を感じているか
- この言葉をどう受け止めただろうか
- この行動は相手にどう映っているか
その想像が、セリフに、選択に、空気に現れる。
NPCは舞台装置ではなく『誰か』として存在し始める。
そしてその関わりが、物語を「追う」ものから「共に歩く」ものに変えていく。
3. プレイヤーの想像力が、卓を即興ドラマに変える
共感は、NPCとの関係だけでなく、PC同士の関係にも力を持つ。
- 仲間の行動をどう受け取るか
- その上で自キャラがどう感じ、どう動くか
感情のやり取りが生まれると、卓には『沈黙のドラマ』が立ち上がる。
セリフの間、目線、言葉にならない気配──
そこに現れる濃度が、ルールとは別の『物語の実感』をもたらす。
4. 『なぜこの人はそうしているのか』と考えるだけで、世界は変わる
共感型プレイは、ボーナスをくれない。
でも、世界が違って見えるようになる。
NPCの何気ないセリフが、ずっと心に残ったり。
PCの選択に、他のキャラが本気で頷けたり。
そのとき、キャラクターはただの役ではなく、この世界に生きている『誰か』になる。
「どう動かすか」より、「なぜそうしているか」を考える
その一歩が、TRPGの物語に命を吹き込んでくれる。
最後に
NPCを『情報』ではなく『人』として見られるプレイヤーは、KPにとって信頼できる共演者になる。
世界に耳を傾けてくれる誰かがいるだけで、物語はやさしく動き出す。
共感は、物語を変える魔法。
それは最強でも最善でもない──
──いちばん優しく、いちばん強い『つながりの魔法』です。
最終更新日:2025年7月27日

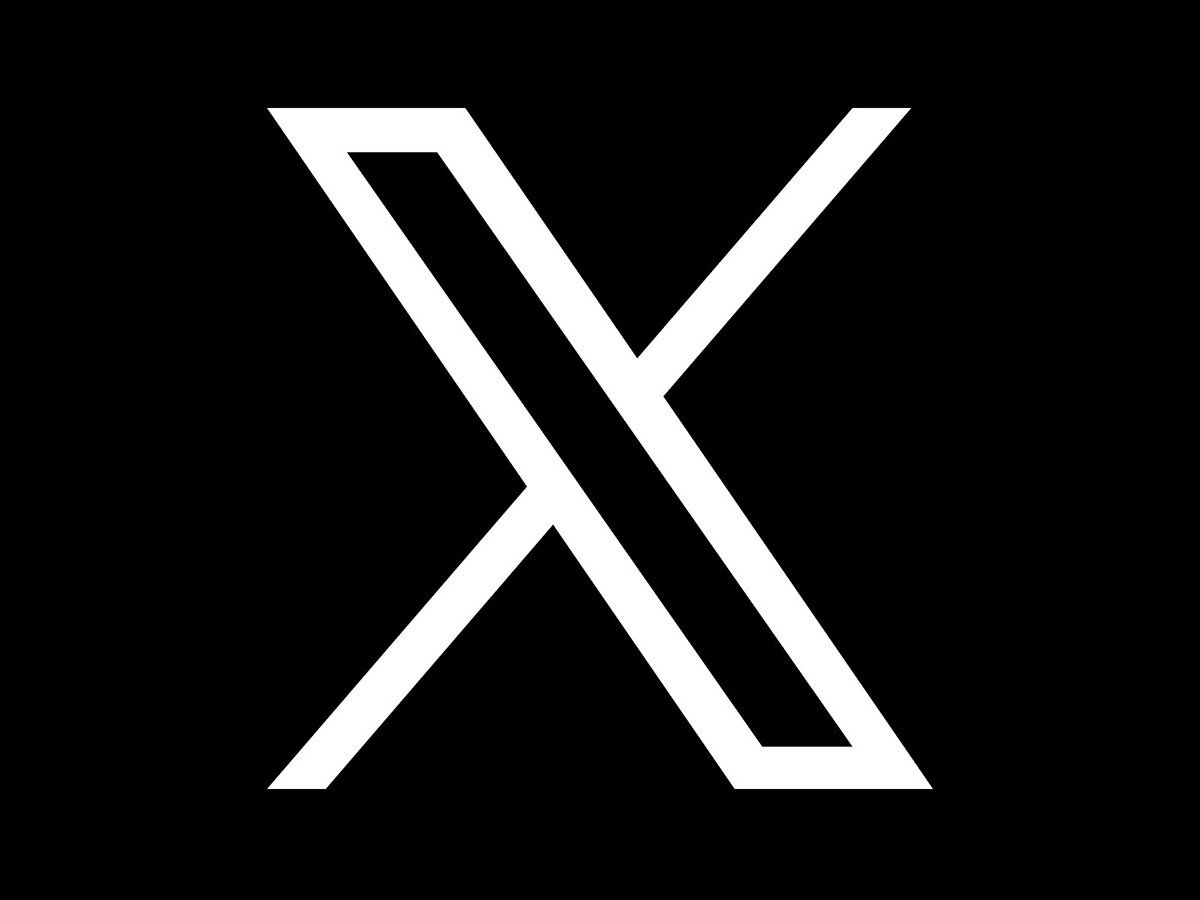 ポスト
ポスト