ルールブック未所持問題
5/10 2025
カテゴリー:プレイ姿勢・在り方編
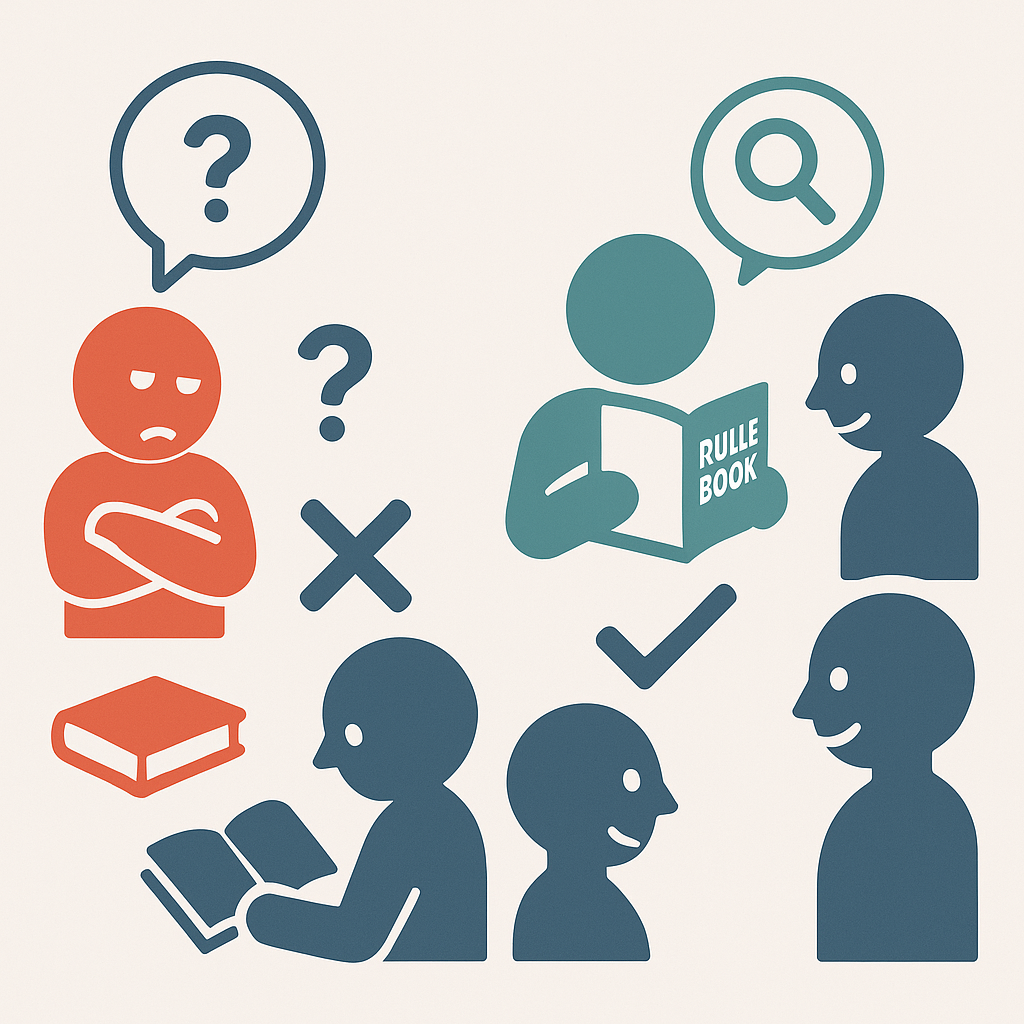
ChatGPTによるこの記事の3行要約
- オンラインでのルルブ未所持は、本質的にグレーではなくアウト寄り。
- GMだけでなく、PL側にも責任がある問題。
- 何度も続けて遊ぶなら、ちゃんと購入して参加しよう。
1. これは主にオンラインセッションでの話です
まず最初に明言しておくと、このコラムで扱う「ルルブ未所持問題」は、オンラインセッションにおける話です。
オフラインセッションで、みんなでルルブを回し読みする──
それはTRPGのごく自然な遊び方であり、「1冊を数人で共有する」ことが前提になっている場面では問題ありません。
問題になるのは、各自が端末や回線を持ち、自由に参照できるオンライン環境において、「所持していないけど、なんとなく参加している」という状況が常態化しているケースです。
2. ルールブックを持たずにTRPGをするということ
これはやや強い表現になりますが、ルールブックを持たずにオンラインでTRPGを行うことは『ゲームソフトを違法ダウンロードして遊んでいる』のとほぼ同じ構図です。
- お金を払うべきところを払っていない
- 本来の手順を踏まずに遊んでいる
- 創作物に対して「無料で済ませる」前提で接している
「なんかそういうものだから」で受け流すには、あまりにも無自覚な『著作物の無断使用』が多すぎる──
それが、今のTRPG界隈にある大きな課題の一つです。
3. 「高い」という気持ちは本当によくわかる
とはいえ、現実問題として、ルールブックは高い。
これはまぎれもない事実です。
CoC6版であれば6,000円前後、他システムでも数千円単位。
学生や収入のない層にとっては、簡単に手が出せる価格ではないことも多いでしょう。
「1回だけ遊んでみたいだけなのに……」
「これから続けるかわからないのに、いきなり数千円は無理……」
その気持ちも、ちゃんと理解できます。
だからこそ、以下のような方法をおすすめします。
4. 「ルルブ未所持だけど遊ぶ」ことが成立する場合
すべてがダメというわけではありません。
以下の条件がそろっているなら、ある程度受け入れられる余地はあります。
- その卓のPL全員が未所持であることを認識している
- GMがそれを了承している(『お試し卓』として案内されている)
- リプレイ動画などの副次的著作物ではない(営利利用を含まない)
- あくまで『継続的な参加前提』ではない一時的なプレイである
このような場合、「体験版」「デモプレイ」としての価値は確かにあります。
GMが丁寧にフォローし、「気に入ったら買ってね」というスタンスを明確にしていれば、『文化の導入』としては成立すると思います。
ただし、それを何度も繰り返して「いつまでも買わない」ようではダメです。
5. GMにだけは、絶対にルルブを持っていてほしい
これは厳密な線引きですが、GMに関しては「絶対にルルブ必須」です。
なぜなら、GMは「ルールを運用し、裁定する側」であり、ルールがわからなければ進行そのものが破綻するからです。
極端に言えば、GMにとってルルブは「教科書」ではなく「機材」であり、「ツール」であり、「現場マニュアル」です。
- 野球で言えばバットとボール
- 音楽で言えば楽譜と楽器
- 演劇で言えば脚本と演出台本
「GMにルルブがないTRPG」は、もはやTRPGとは呼べません。
6. 絶対に見てはいけない『転載サイト』
いまだに見かけるルールブックの全文転載サイト。
ページをそのまま文章化し、誰でも読めるようにしている。
これはもう完全に著作権違反です。
明確に「やってはいけない」ラインを越えています。
- 検索して出てくるから見ていい
- 『公式』って書いてあったから大丈夫
- みんな見てるから平気
──どれも通用しません。
ただ、「それがダメなことだと知らなかった」人もいます。
だからこそ、もしそういう人を見かけても、すぐに責めるのではなく、まずは教えてあげてください。
「それ、実は公式じゃない転載サイトだから、気をつけた方がいいよ」
その一言が、界隈の健全さを守ることにもつながります。
7. 続ける気があるなら、ルルブを買おう
TRPGを何度か遊んでみて、「楽しいな」「またやりたいな」と思ったらどうか、ルールブックを買ってください。
ルルブは、「遊び方が書いてある本」じゃなく、「遊ぶために必要なツール」です。
そして、そのお金は「TRPGという文化を支えてくれている人たち」への応援になります。
- ルールを作ってくれた人
- イラストを描いてくれた人
- 編集・印刷・流通に関わってくれた人
そのすべてがあって、私達は『物語を遊ぶ』ことができている。
だから、ほんの少しでもいいから、「遊ぶ側からの感謝とリスペクト」をお金で返す。
それが、TRPG文化を持続させるという意味での、最低限の誠意だと思います。
8. 無料で始められる選択肢もある
「いきなり数千円はちょっと……」という人のために、無料で遊べるTRPGという選択肢も存在します。
たとえば『エモクロアTRPG』などは、公式ルールブックが無料公開されており、誰でもルールブックを所持する事ができます
また、TRPGとは少し違いますが『マーダーミステリー』というジャンルもおすすめです。
これは基本的にGMがシナリオを持っていれば遊べるため、参加者が書籍を買わずに済むという点でハードルが低いです。
もちろん、いずれ幅広いTRPGの本格的な世界に触れたいならルルブの購入は避けられませんが、TRPGを始める足がかりとしてはこういった選択肢も十分アリだと思います。
まずは一歩。始め方は、ひとつじゃありません。
最後に
ルールブック未所持問題は、センシティブな話題です。
でもだからこそ、ちゃんと語らなければいけないと思っています。
「別にいいじゃん」ではなく、「どうあるべきか」を考える。
その姿勢こそが、プレイヤーとしての『文化との関わり方』に直結する。
あなたがTRPGを好きだと思っているなら──
どうか、その『好き』を、少しだけ行動に変えてみてください。
まだ買ってない人は、ぜひ一度公式で調べてみてください。
きっと、『買ってよかった』と思えるルールブックがそこにあります。
最終更新日:2025年7月26日

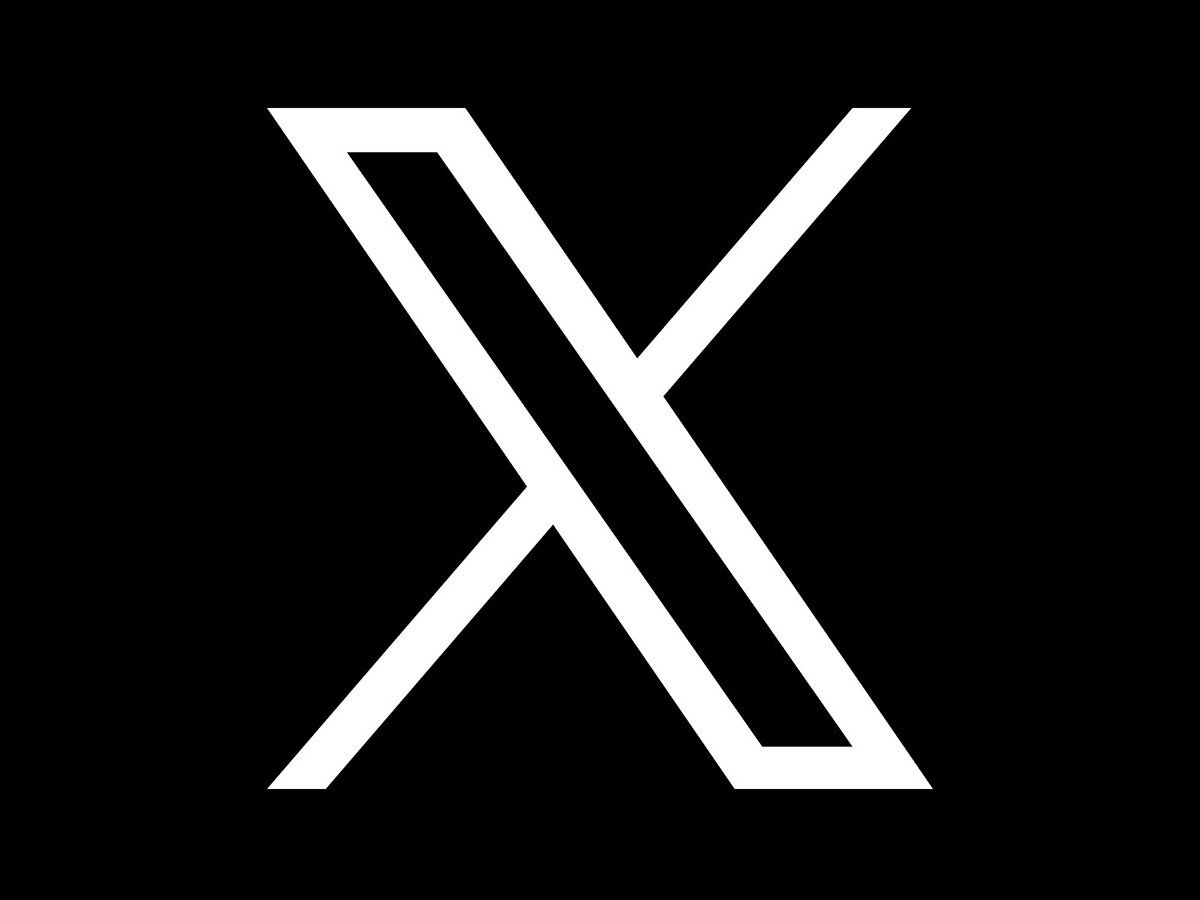 ポスト
ポスト