『行動宣言』と『心情の演技』を分けて考えてみる
6/20 2025
カテゴリー:プレイ姿勢・在り方編
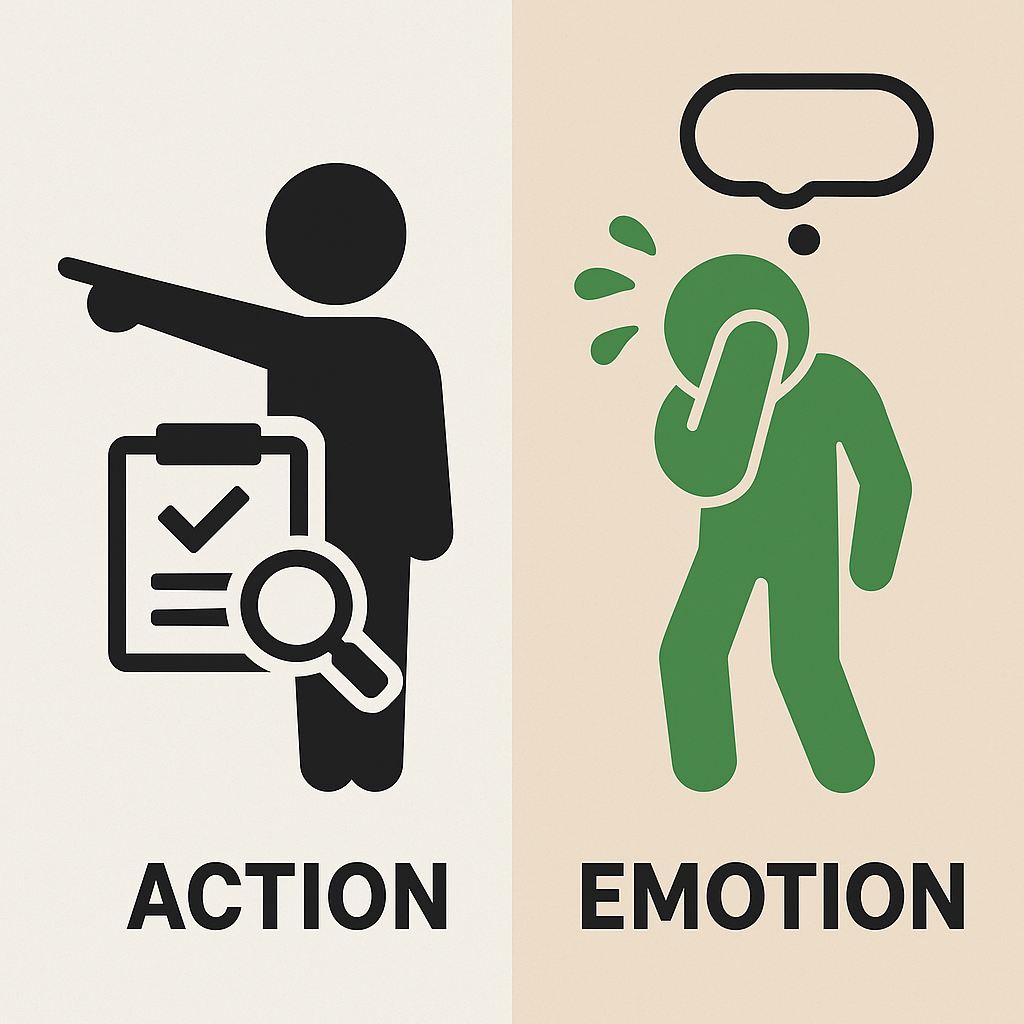
ChatGPTによるこの記事の3行要約
- 行動宣言は、卓を進めるための「情報」。
- 心情の演技は、物語を深くするための「表現」。
- この二つを分けて考えるだけで、プレイの伝わり方は大きく変わる。
1. 混ざりやすいけれど、違うもの
TRPGのプレイ中、「探索者がこう動きます!」という行動宣言と、「今、このキャラはどう感じているか」を表す心情の演技が、しばしばごちゃ混ぜに扱われる場面があります。
別にそれが悪いわけではありません。
でも、ここをちゃんと分けて意識するだけで、プレイの質がぐっと上がります。
- 行動宣言は卓の進行を支えるもの。
- 心情の演技は物語の深度を支えるもの。
役割が違います。
2. 行動宣言は「情報」として明確に
行動宣言は、まず明確に言ったほうが良いです。
- 誰に何をするのか
- どの技能を使うのか
- その意図はどういうものか(簡潔に)
これがあやふやだと、GMも他のPLも「結局どうなったの?」と混乱します。
だから、まず行動ははっきり言うのが基本です。
たとえば…
- 「机の引き出しを開けて中を確認します」
- 「銃を構えてドアの方に照準を向けます」
- 「NPCに〈説得〉を振って、落ち着かせようとします」
これだけで場はぐっとスムーズに進みます。
3. 心情の演技は「味付け」として丁寧に
一方、キャラクターの心情や表現は、
行動宣言とは別枠として扱ったほうがいいです。
- なぜその行動に至ったのか
- その時の表情、声、態度はどうか
- 内心はどう揺れているか
これらは「こうする!」と言ったあとに、演技として『添える』と非常に映えます。
たとえば…
「銃を構えてドアの方に照準を向けます」
→ (震えた声で)「……誰、誰かいるの……?」
行動宣言だけでは機械的に見える動きが、心情を重ねることで『キャラがそこにいる』ようになります。
この順番を意識するだけで、卓の空気が一段階変わります。
4. 混ぜすぎると起きる弊害
逆に…
- 心情の演技だけをして行動が曖昧だったり
- 行動宣言の中に長々と心情まで詰め込みすぎたり
すると、場が流れづらくなることがあります。
PL「この状況で冷静を装いつつ、でも内心はもう限界ギリギリで──」
GM「で、何をするの?」
こうなった経験、ないでしょうか。
もちろん、気持ちを込めるのは大事。
でも、「行動は行動、演技は演技」という意識を持っておくと、整理されたロールプレイになります。
5. 上級者ほど、この切り替えが自然にできている
よく「ロールプレイがうまいなあ」と思うPLはこの切り替えのリズムが自然です。
- まず行動をはっきりと卓に提示
- 次にそのキャラの『人間らしさ』を演技で肉付け
この順番を繰り返すことで、テンポは崩さず、物語の厚みは保つという両立ができています。
これは意識すれば、誰でもできる技術です。
最後に
TRPGは「演技力がすべて」でも「効率がすべて」でもありません。
行動と心情、それぞれの役割を理解して場に出すことが、全員にとってわかりやすく、心地よいプレイにつながります。
次にセッションでプレイするとき、
「今は行動を伝えるとき」「今は心情を見せるとき」
その意識をほんの少し持ってみてください。
それだけで、キャラも物語も、もっと鮮やかに立ち上がるはずです。
最終更新日:2025年7月26日

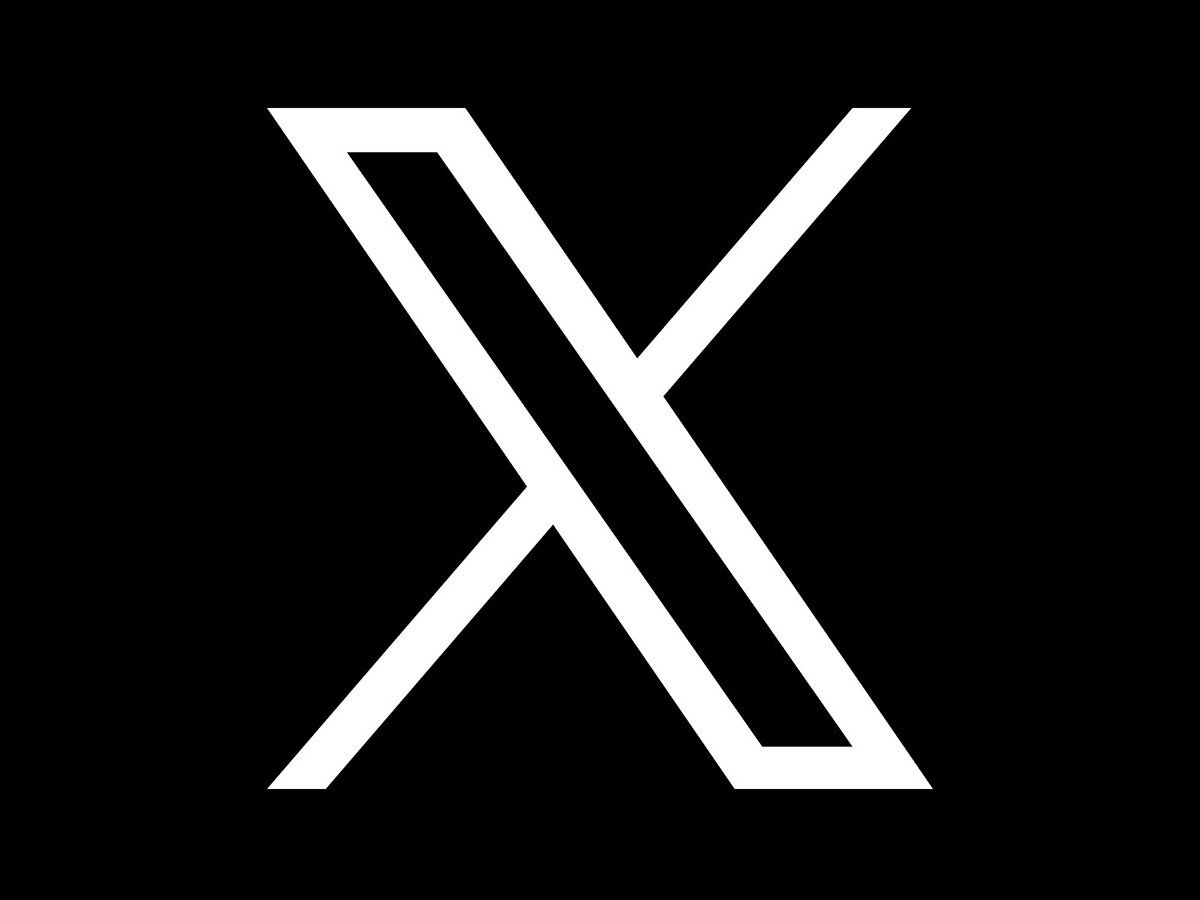 ポスト
ポスト