キャラ設定を白紙で出す
4/29 2025
カテゴリー:キャラクター論・設定運用
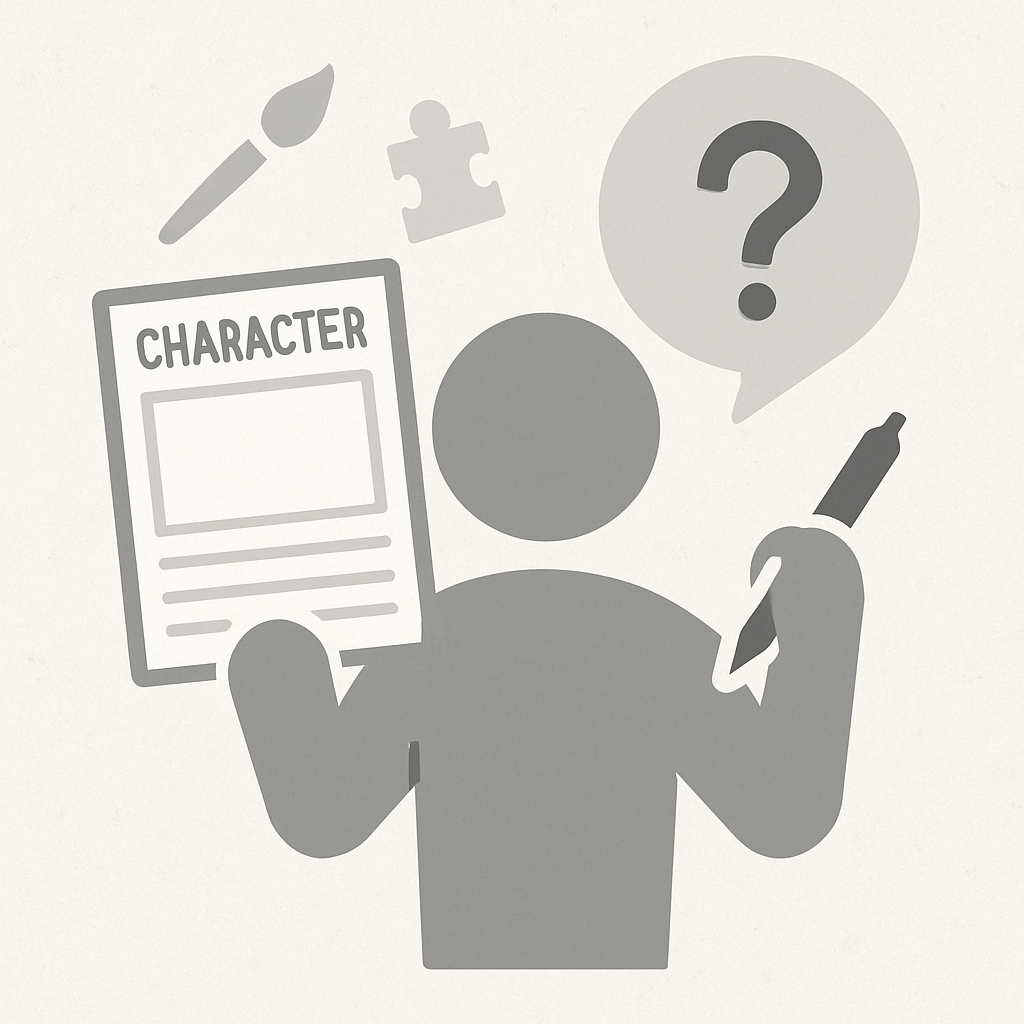
ChatPTによるこの記事の3行要約
- 白紙提出は放棄ではなく、即興でキャラを見つけていく選択でもある。
- ただしGMには何も伝わらないため、動きと反応で補う責任が生まれる。
- 白紙は空白ではなく、卓の中で埋めていくための余白だ。
1. 「設定を決めない」という選択が、自由をくれる
キャラを作るとき、背景や性格を細かく練る人もいれば、「まずは動かしてみてから決めよう」というタイプの人もいる。
いわゆる、キャラシに設定を一切書かない『キャラシ白紙提出』。
これには一定の批判もあるけれど、私自身、実はその感覚がよくわかる。
というのも、自分もかつて『白紙提出』を選ぶプレイヤーだったからだ。
- 世界観のなかで何を感じるか、
- GMの描くNPCに対してどう反応するか、
- 他のPCとの関係性がどう変わっていくか。
そういった『外からの刺激』に身を預けながら、キャラを少しずつ「見つけていく」遊び方。
それは、ある種の即興性と自由を大切にする姿勢であり、決して『考えていない』とか『丸投げ』ではないと、私は思っている。
2. 白紙は「伝わらない」という前提がある
ただ、そのスタイルには明確な弱点がある。
それは、GMにとって『何も伝わらない』ということだ。
たとえば、キャラの性格も口調も動機も書かれていないキャラシを見て、GMはセッション前に何を想像すればいいのだろう。
- どんな言葉遣いをするのか
- どういう事件への関わり方を想定しているのか
- どんなテーマをぶつけると響くのか
何ひとつ判断材料がない状態では、物語の投げかけ方を組み立てにくくなる。
特に、セッション開始前のキャラシ確認だけで全体構成を考えるGMにとっては、白紙キャラは「空白地帯」になってしまう。
これは悪気がないからこそ生じる、『スタイルのズレ』によるすれ違いなのだ。
3. 白紙提出は「即興を楽しむ」準備のうちにする
だから、白紙で出すこと自体は否定しない。
ただし、それは『自由に遊ぶための責任』も背負っているということを忘れてはいけない。
- プレイ中、GMや他PLに混乱を与えないよう、『キャラの芯』を素早く立てる
- 設定を後出しにする場合は、その都度『シナリオの流れと矛盾しないよう慎重に提示』する
- NPCや状況の描写に対して、「無反応」ではなく「試しにでも動いてみる」姿勢を持つ
白紙提出というのは、『何も書いていないキャラ』ではなく、『プレイで描くための余白を残したキャラ』なのだ。
だからこそ、その余白をどう埋めるかは、自分にかかっている。
4. 書かない選択をしたなら、丁寧に『動いて示す』こと
セッションが始まってからキャラを描いていくスタイルは、とても面白いし、時に『生まれたての感情』がシナリオを揺さぶる瞬間もある。
でもそのぶん、周囲は常に『様子を見ている』状態になる。
- 「この人、どんな人なんだろう?」
- 「どう扱えば物語が進むだろう?」
- 「踏み込んでも大丈夫だろうか?」
だからこそ、白紙で出したプレイヤーが「受け身にならず、プレイの中でしっかり応答する」ことが必要だ。
- 少しでも話す、動く、反応する
- そこに生まれた『感情』を、自分でも言葉にしていく
- 気づいたら、『キャラシに書いてない設定』が仲間にも伝わっていた
それができると、白紙はただの空白じゃなくなる。
『卓で生まれた関係性そのものが、キャラ設定になる』瞬間が訪れる。
最後に
キャラ設定を白紙で出すというのは、紙の上では『何も語らない』
けれど、プレイの中で『全部語る』という選択だ。
だからこそ、その選択には、それをやるだけの姿勢と感度が求められる。
うまくいけば、それはとても豊かな遊び方になる。
でも、放置すれば、ただ『誰にも読まれないキャラ』になってしまう。
だから最初から決めすぎなくていい。
けれど、「動きながら見せていく努力」は、絶対に忘れないようにしたい。
白紙のキャラも、物語の中でちゃんと『色』になる。
それを信じて、丁寧にプレイを重ねていけばいい。
最終更新日:2025年7月28日

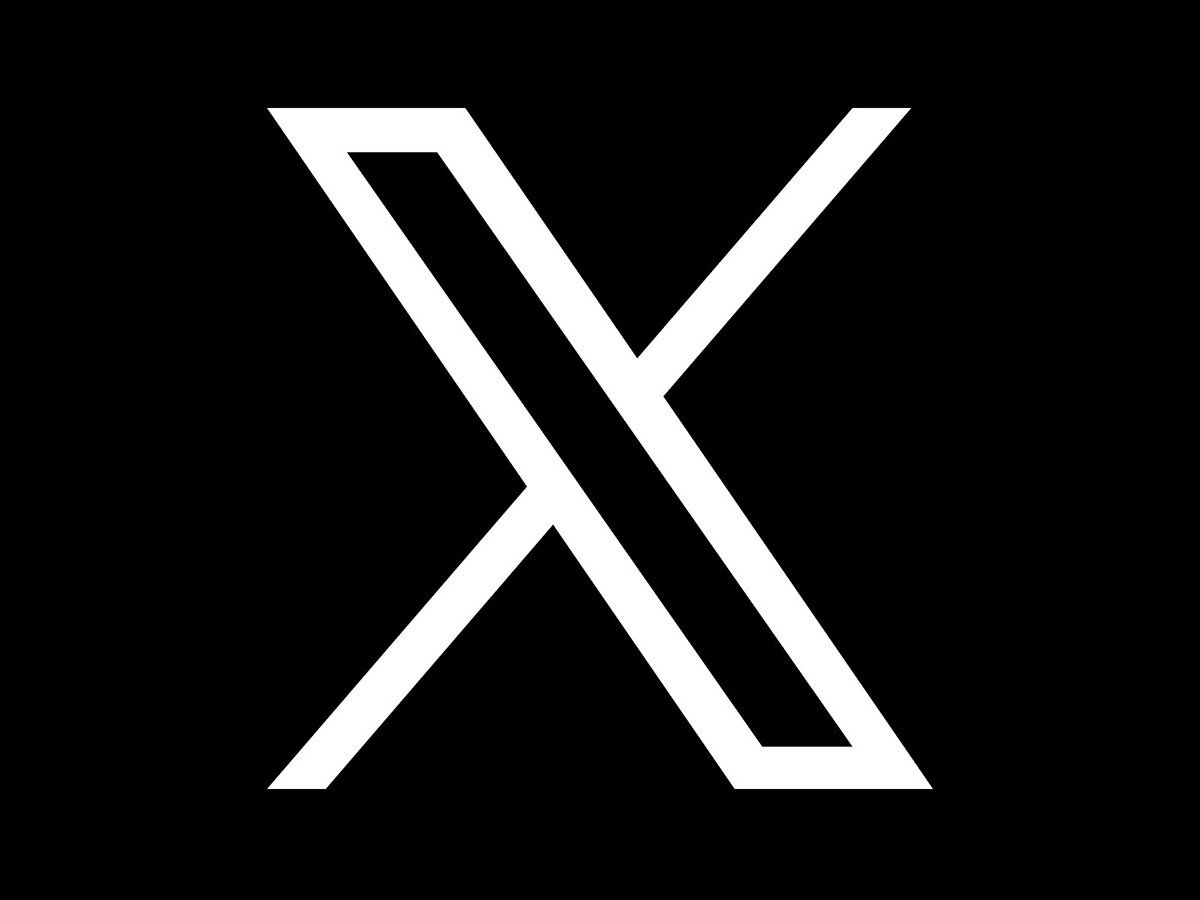 ポスト
ポスト