アイデアは知識を超えないのか
5/8 2025
カテゴリー:実体験を基にした個人的な話

1. 「知識がないと発想できない」は、少し違う気がする
TRPGを遊んでいて、見かけた意見がある。
「アイデアを出すには、まず知識が必要だよ」
…なるほど。たしかに一理ある。
ホラーシナリオを書くなら、構造や文脈を知っていた方が強い。
キャラ設定を作るなら、年代背景や文化を踏まえた方が深みが出る。
演出を考えるなら、映画的センスや演劇的技法を知っていると映えることもある。
でも、それを「知識がなければ、何も生み出せない」と言い切ってしまうのは、ちょっと乱暴だと思う。
2. 知らないからこそ、描ける世界がある
TRPGの中には、「あまり知識がない」からこそ予想外の面白さを生む瞬間がたくさんある。
- 舞台設定のズレが逆に『異世界感』になった
- 怖い演出のつもりが奇妙でユニークな展開になった
- キャラの言動が現実的ではないぶん、印象的だった
たとえば、クトゥルフ神話TRPGでは、『神話生物を知らないPL』の方が物語の衝撃が強くなることがある。
「知らない」という『欠落』が、そのまま物語への没入感になる。
知識があると、その知識に縛られる。<
「これはありえない」
「そんなのリアルじゃない」
そうして、思考がブレーキをかけ始める。
でも、知らない人は遠慮しない。
『自由な突拍子』で、世界を広げてくる。
知識はツールであり、必須条件ではない。
それがTRPGという遊びで、よく見える。
3. 「直感」と「偶発性」も、アイデアの仲間たち
創造の場では、『偶然から生まれた発想』というものも多い。
- プレイヤーのミスから生まれたキャラの個性
- 台詞のかみ合わなさから、想定外のシナリオ分岐
- ダイスの出目が引き起こした『想像を超えた場面』
どれも「知識」だけでは説明できない流れだが、それらはすべて物語を前に進めるエネルギーになる。
「整った知識」ではなく、「不確かな感性」だからこそ、場にリアリティが生まれることもある。
4. 「学び」は、あとからでもついてくる
もちろん、知識が不要と言いたいわけじゃない。
むしろ知識があとからアイデアを支える場面はたくさんある。
- 思いついた設定に整合性を与える
- 世界観の構築を深めてくれる
- 物語の骨格にリアリティを加えてくれる
でも大事なのは、「先に知識がないと発想できない」と思い込まないこと。
だから、知識は出発点ではなく、『伴走者』でいい。
最後に
「アイデアは知識を超えない」──たしかに、そういう側面もある。
でも、TRPGの中では、それが逆転する瞬間を何度も見てきた。
「知識がないからこそ飛べた想像」
「間違いだったからこそ面白かった展開」
TRPGの魅力は、「整った人間」が遊ぶものではなく、『不完全な人間』が集まって、手探りで物語を編むところにある。
たとえ知識がなくても、「こんなキャラを動かしたい」「こういう物語を描いてみたい」と思ったら、まずは遠慮せず、発想を形にしてみてほしい。
『知らないからこそ、出せる手がある。』
TRPGは、その面白さをちゃんと肯定してくれる遊びだから。
最終更新日:2025年7月30日

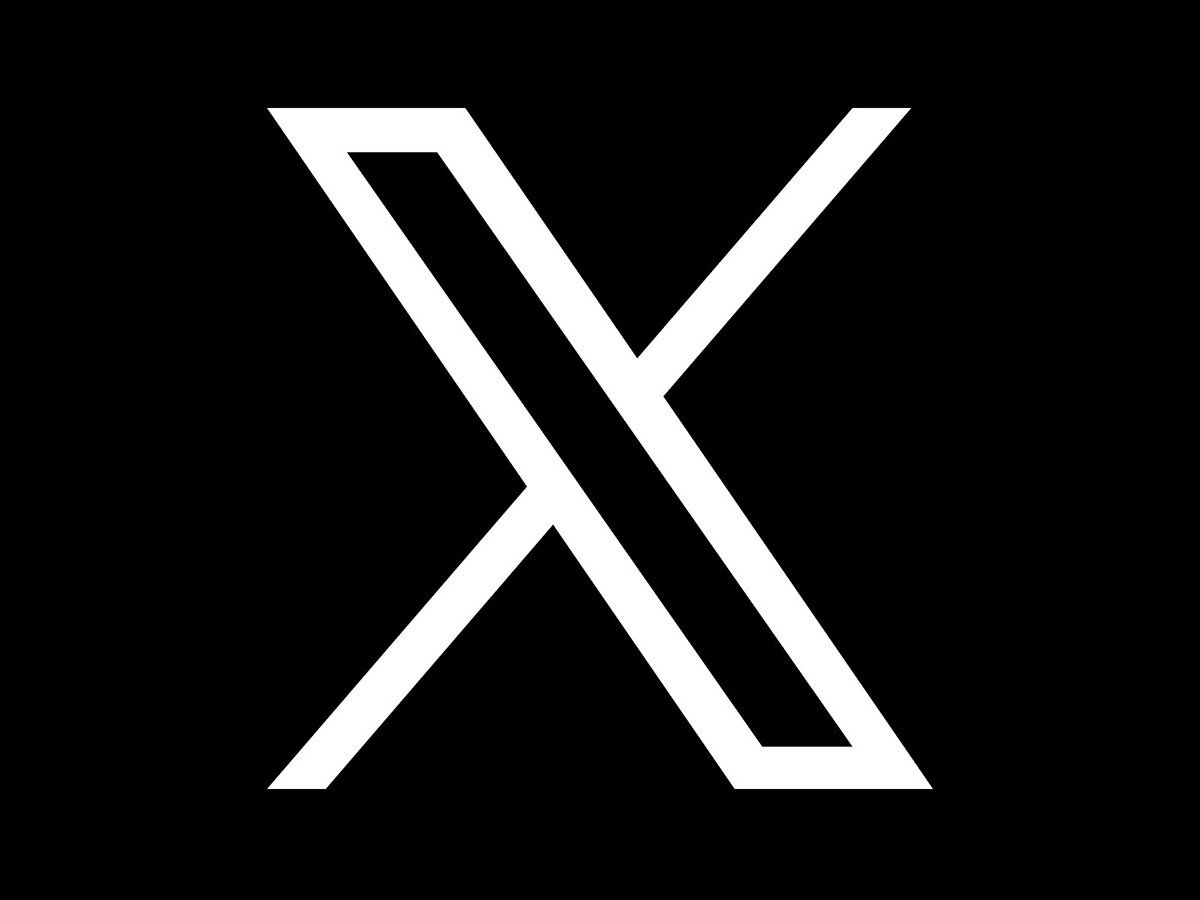 ポスト
ポスト