『ハウスルール』の扱い方
5/9 2025
カテゴリー:GM・物語との関わり編

ChatPTによるこの記事の3行要約
- ハウスルールは自由の象徴ではなく、あくまで遊びやすくするための「味付け」。
- 面白くても複雑すぎるルールは、使われなくなった時点で負担になる。
- 既存ルールを壊さない範囲での補完こそが、参加者に優しいハウスルールになる。
1. ハウスルールは『味付け』であって、『本編』ではない
TRPGを遊んでいると、時々目にするのが「うちの卓では、こうしてるんですけど」という一言。
いわゆる『ハウスルール』というやつだ。
- 成長ルールを独自に変更
- クリティカル・ファンブルの扱いを拡張
- 魔術や神話生物に独自設定を追加
- 戦闘ルールをより戦略的にカスタマイズ
どれも、それ自体は悪いことじゃない。むしろ、「もっと面白くしたい」という意図から生まれる発想であり、創意工夫の証だ。
けれど、ハウスルールは「味付け」であるべきだということは、常に頭に置いておきたい。
本来のルールが分からなくなるような『改変』は、自由を超えて『負担』になる。
2. 自分の卓で試したハウスルールの話
これはクトゥルフ神話TRPG(6版)の話になるけれど、自分の卓でもかつてちょっと凝ったハウスルールを採用していたことがある。
「アイデア、幸運、知識」などの『特殊ステータス』がクリティカルまたはファンブルしたとき、それぞれ対応する『技能群』から1つ選んで成長チャレンジができる。
──というルールだ。
「直接技能じゃない出目も成長に繋がったら嬉しいよね」という気持ちで入れたもので、最初のうちは「発想が面白い!」と好評だった。
……けれど、現実はやや違った。
- 「この技能群ってどれに対応してたっけ?」
- 「アイデアで成長判定振るの?」
- 「この技能、今のシーンに関係なくてもいいの?」
──処理が煩雑になり、次第に誰も触れなくなった。
面白くても、難しいと使われない。
この体験は、ハウスルールの『限界』と『現実』を教えてくれた。
3. ルールの『補完』くらいが、ちょうどいい
ハウスルールが機能するかどうかの分かれ目は、「既存ルールをどれだけ崩していないか」だと思っている。
- 曖昧な処理を明文化する
- KPの裁量で決まる部分に指針を加える
- 遊びやすくするために演出に幅を持たせる
この程度の『補完』くらいにとどめておくと、トラブルは少ない。
とくに初対面のPLや短期卓では、突飛なハウスルールは『壁』になるより先に、『地雷』に見られるリスクすらある。
それは、「自由な遊び方」を否定されているからではない。
「前提が共有されていないまま、未知の環境に連れてこられること」に対する警戒なのだ。
だからこそ、ハウスルールは「その卓の特色」ではなく、「遊びの円滑剤」として使うくらいがちょうどいい。
最後に
TRPGは『自由な遊び』だから、ルールをカスタムするのも自由だ。
でも、その自由はいつでも「参加者の負担と不安の少なさ」とセットであるべきだと思う。
面白いけど、ややこしい。
正しいけど、楽しくない。
そんな風になってしまったら、本末転倒だ。
ハウスルールは、あくまで『補助輪』であり、「これがあると、もう少し気持ちよく走れるね」くらいが、たぶん一番いい。
最終更新日:2025年7月27日

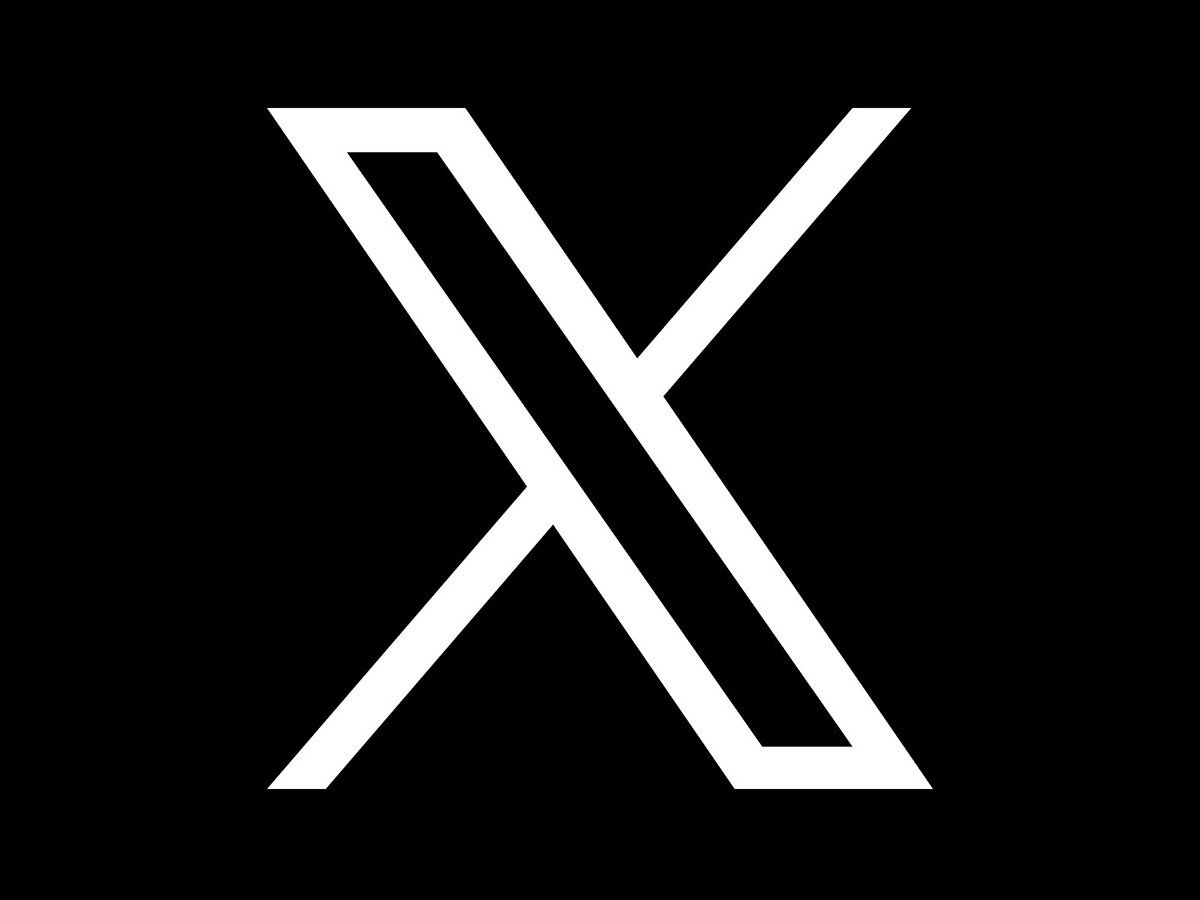 ポスト
ポスト