推理は『当てる』ことより『広げる』こと
5/5 2025
カテゴリー:実践・技術寄りのテーマ
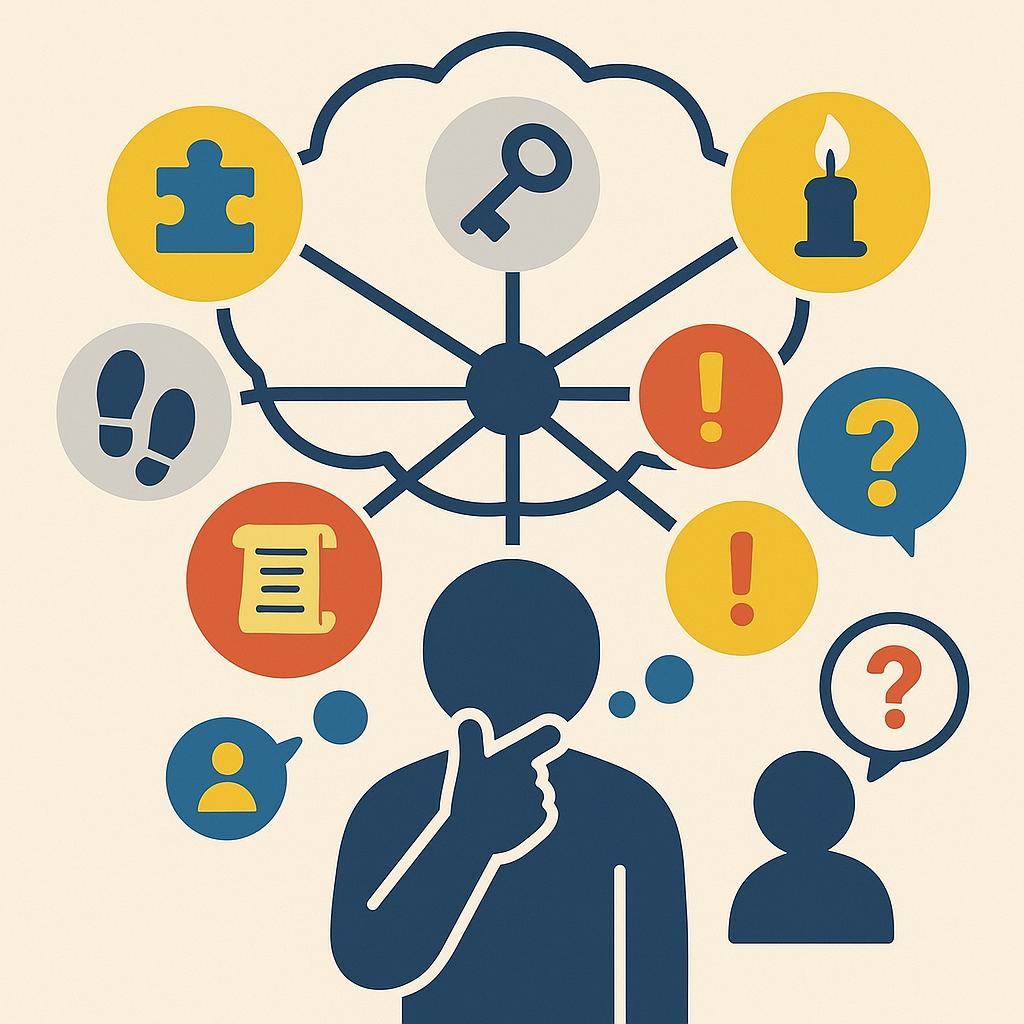
ChatPTによるこの記事の3行要約
- 推理を当てに行く姿勢は、物語の選択肢を狭めてしまうことがある。
- 大切なのは正解より、仮説や違和感を共有して思考を広げること。
- 推理は競争ではなく、全員で納得できる物語に近づくための行為だ。
1. 「当てにいく推理」は、時に物語を狭める
TRPGにおける推理──それはセッションの醍醐味のひとつだ。
複雑な事件、不可解な現象、ちりばめられた手がかり。
そこに意味を見出し、真実に近づいていく過程は、誰にとってもスリリングで楽しいものだ。
でも、ここで忘れてはいけないことがある。
「推理を当てること」だけに集中してしまうと、物語は急に『終着点』になってしまう。
いわゆる「犯人当て」や「真相一点狙い」の姿勢は、それが外れた瞬間に失速してしまいがちで、それが当たった瞬間に、ほかの選択肢や世界が『なかったこと』になってしまう。
推理は、『謎を一発で撃ち抜く』ためのものではない。
シナリオの中にある複数の可能性を『試して、比べて、拾い上げていく』ための動作だ。
つまり、「広げる」ことが先にある。
2. 情報をつなぐより、「視点」を増やしてみる
探索の途中、手がかりが増えてきた時、「つまりこういうことじゃない?」とまとめようとする人が出てくる。
それはとてもありがたいし、場を動かすためにも必要な動きだ。
でも、そこで他の人が「それで決まり」と感じてしまうと、新しい仮説が生まれなくなってしまうことがある。
ここで大切なのは、『仮説』は結論ではなく、問いかけのきっかけだということ。
プレイヤーの推理は、「真相を述べる」より、「別の見方を持ち込む」ためにある。
- 「もしかして、このNPC、味方じゃなくて第三勢力なんじゃない?」
- 「このメモ、わざと落とされたものかもしれないよね」
- 「『過去』の出来事って、そもそも誰の証言が元なんだっけ?」
こうした意見は、「正解」じゃなくていい。
でも、それがあるだけで、場の思考は広がる。
KPもそれを拾って展開に組み込める。
結果として、シナリオの解像度が上がり、プレイヤー全体が『深く潜れるようになる』。
3. 推理は『共有』してこそ意味がある
もうひとつ、推理において見落とされがちな視点がある。
それは、「推理を独りで抱え込まない」こと。
「分かっちゃったから、言わないでおく」は、時に場の停滞を招く。
逆に、「分かったことを全部一気に語ってしまう」のも、他の人の思考の余地を奪う。
だからこそ、推理は『共有』という形で出すのがベストだ。
- 「これ、気のせいかもしれないけど、ちょっと変じゃない?」
- 「ここ、他に読み方あるかもって思ったんだけど……」
- 「こう考えると辻褄は合うけど、納得いかないんだよね」
このように、『問い』や『引っかかり』のまま出すことができると、他のプレイヤーがその上に意見を重ねられる。
そして、それが重なっていった先にこそ、『共通の推理』が生まれていく。
TRPGは「全員で作る物語」だ。
だから、推理も『全員で見つけていく』ほうが、気持ちがいいし、深くなる。
4. 「正解より、納得できる展開」を目指そう
ときどき、「自分の推理が当たったことだけが嬉しい」というプレイスタイルを見かける。
それは確かに快感はある。が、それが『自分しか満足していない』状態になってしまうと、卓の温度が下がる。
むしろ、たとえ推理が外れても、「みんなでそれを確かめに行く過程」が面白かった。
そんなセッションの方が、ずっと記憶に残る。
TRPGにおける推理とは、犯人当てではない。
『自分たちが選んで歩いてきた物語に、納得できるかどうか』を確認していく作業だ。
だから、たとえ真相が当たらなくても、「この結末にたどり着く流れ、面白かったよね」と言えたら、それが正解なのだ。
最後に
推理は、『ひとつの答え』にたどり着くためではなく、『みんなで、ひとつの答えにたどり着けたことを喜ぶため』にある。
問いを出し、選択肢を残し、空気を動かし、物語を耕す。
その力を持っている人は、『答えを知っている人』ではなく、『問いを共有できる人』だ。
次に推理する場面がきたら、こう考えてみてほしい。
──「何を言うか」より、「どうやってみんなを巻き込めるか」を。
あなたの問いかけが、場を広げ、物語を面白くする。
それこそが、TRPGにおける『上級者の推理』だから。
最終更新日:2025年7月28日

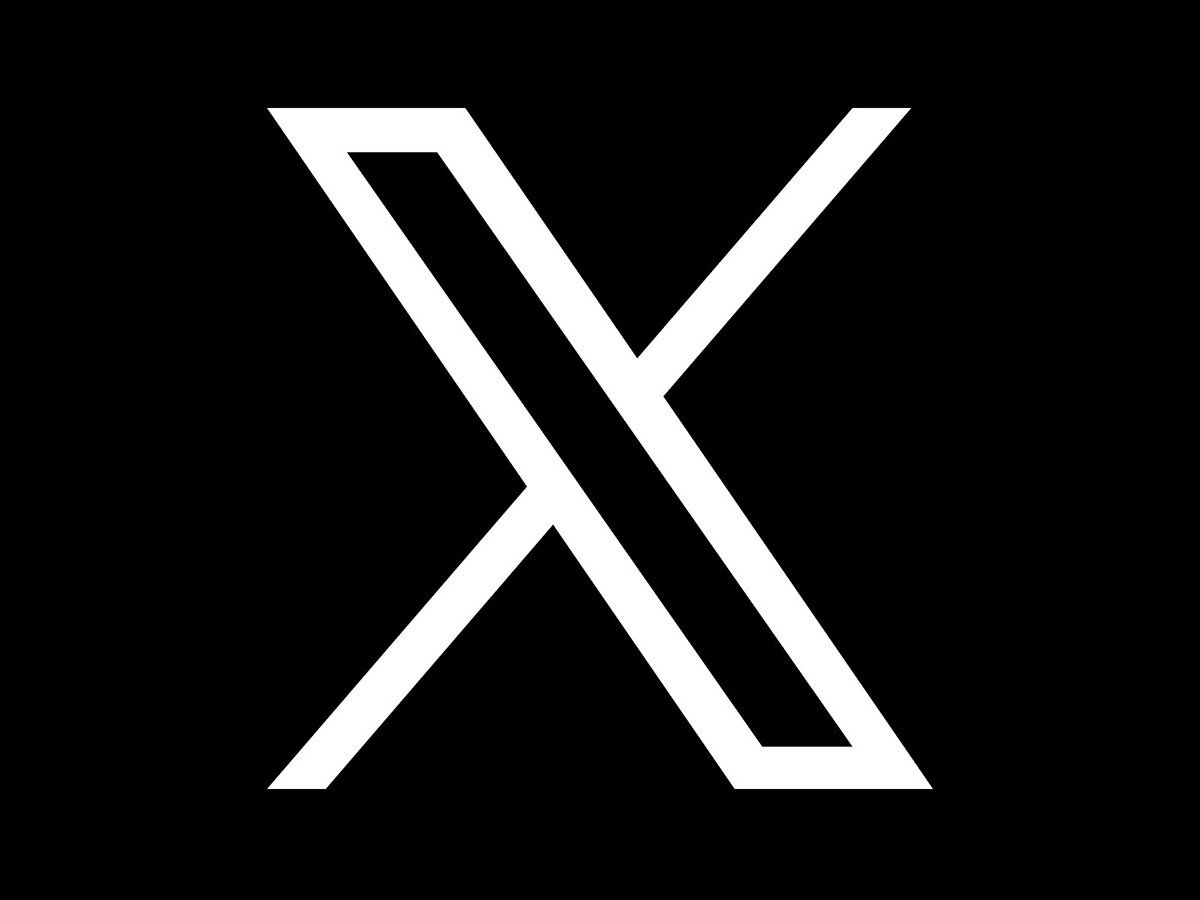 ポスト
ポスト