ファンブル処理
4/29 2025
カテゴリー:演出・美学・語り口編

ChatPTによるこの記事の3行要約
- ファンブルは罰ではなく、物語を別方向へ転がす装置として扱える。
- 大切なのは嫌がらせにせず、納得できる偶然として描くこと。
- 失敗をきっかけに人が動いたとき、停滞していた物語が息を吹き返す。
1. ファンブルって、どういうルールだったっけ?
※便宜上、CoC6版をベースに話を進めます。
ファンブル(致命的失敗)と聞くと、「96〜100で発生」というのがプレイヤーの間では一般的な認識かもしれません。
けれど、実はこの定義、ルールブック上は少し異なっています。
クトゥルフ神話TRPG(6版)における本来のファンブルの定義は以下のとおりです。
- 戦闘や危険な状況においてのみ、96〜100をファンブルとする。
- 探索などの『非危険』な行動においては、100のみがファンブル扱い
つまり、「常に96〜100がファンブル」というのは拡張ルールであり、卓やGMの裁量に委ねられているものです。
2. あえて『厳しめファンブル』を導入する理由
私自身も、自分がGMのセッションでは戦闘以外でも96〜100をファンブルとして扱っています。
これは、単純に「失敗しやすくしたい」という意図ではありません。
『物語に緊張感が生まれる』からです。
- 調査中に重要書類をうっかり破いてしまった
- 隠れていたはずが、盛大にくしゃみをして見つかってしまった
- 説得のつもりが、かえって相手の逆鱗に触れてしまった
こうした『ちょっとした事故』が物語の温度を変える瞬間は、プレイヤーにとってもGMにとっても、予期しないスパイスになります。
ただし、これは「事故=罰ゲーム」になってしまうと逆効果。
ファンブルを広く導入するなら、それが物語に『面白く作用する』ための工夫が必要です。
3. ファンブル処理のコツは、『納得できる偶然』にすること
ファンブル処理で大切なのは、ただの『嫌がらせ』にしないこと。
プレイヤーが「その結果、物語が面白くなった」と思えるように、『筋の通ったトラブル』として描くことが必要です。
以下はファンブル処理の際のコツです──
- ✅【1】『世界の反応』として処理する
キャラ自身の能力不足ではなく、外部要因による失敗として描くとリアリティが保たれます。
- 「鍵を開けようとしたら、向こうからドアが開いて突き指した」
- 「質問しようとしたら、相手の電話が鳴って中断された」
- ✅【2】『別の方向に進む』誘導にする
ファンブルで道が封じられる代わりに、別のルートを示す。
- 「この人物からは情報が得られず不信がられたが、代わりに別の情報源が浮上する」
- 「証拠は壊れたけれど、その痕跡から違う仮説が導き出される」
- ✅【3】『キャラの人間味』を強調する演出にする
失敗をキャラの個性に昇華させる。
- 「いつも冷静なキャラが、今回だけ動揺して手が滑る」
- 「ポンコツ扱いされてたキャラが失敗しても愛される空気になる」
- ✅【4】『失敗したことで他人が動く』構図にする
ファンブルを他PCの活躍のきっかけにする。
- 「誰かが失敗した後、別のPCがカバーして信頼が芽生える」
- 「行き詰まった空気がファンブルをきっかけに動き出す」
4. 失敗は、動かない物語を『転がす装置』になる
ファンブル処理がうまくいくと、そのミスが場面の主役になる。
- 一言のしくじりから、NPCの態度が変わる
- 情報のミスリードが、新たなドラマを生む
- 危機的状況に追い込まれたからこそ、キャラの信念が試される
これこそ、TRPGの醍醐味だと思うのです。
「成功すれば物語が進む」「失敗すれば停滞する」という構図から脱却して
「失敗しても動ける」「ミスが物語を深める」と考えるプレイスタイル。
それを支えるのが、上手なファンブル処理なのです。
最後に
だから、ファンブルが出たときは、落胆しなくていい。
むしろ、「ここから、面白くなるぞ」と思っていい。
失敗は、物語が動く音。
処理に工夫があれば、事故はいつだって演出に変わる。
最終更新日:2025年7月30日

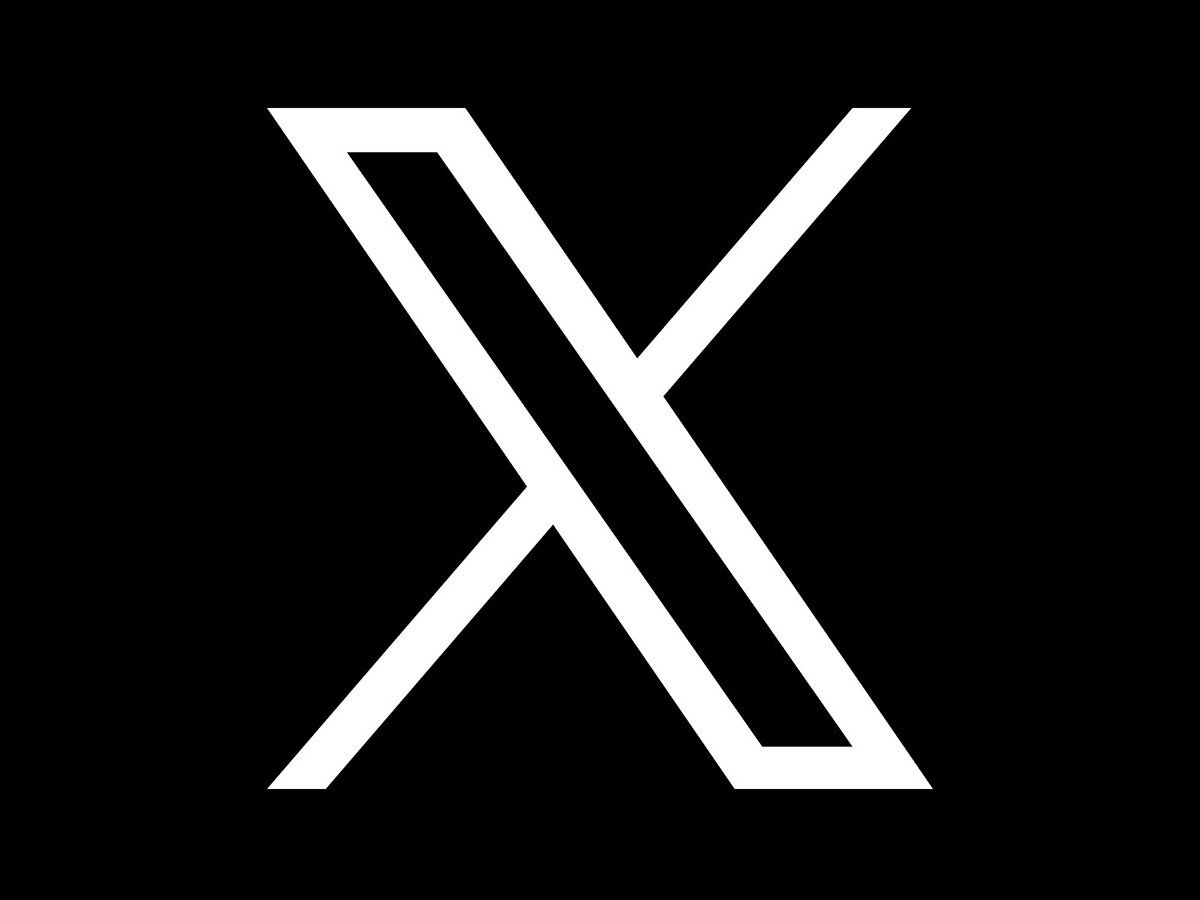 ポスト
ポスト